-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
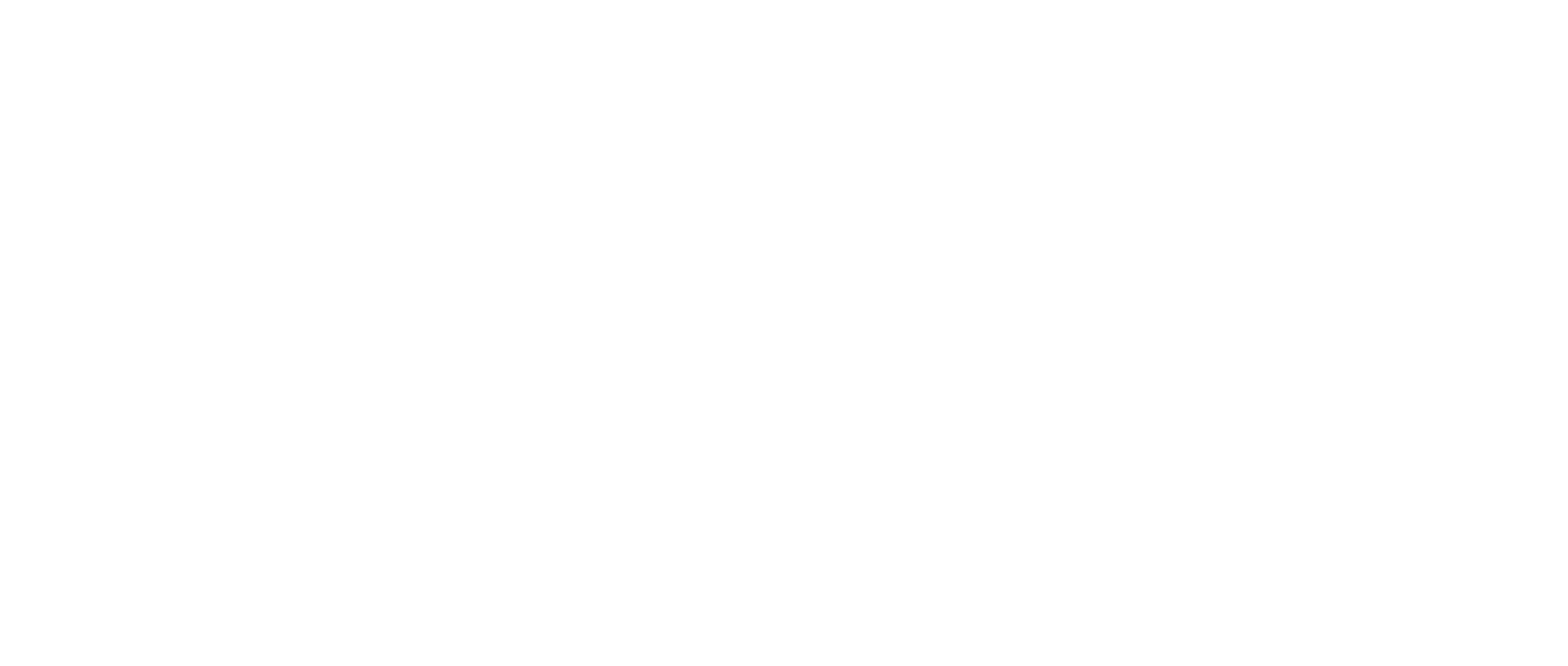
皆さんこんにちは!
株式会社谷研、更新担当の富山です。
~見た目だけじゃない、機能と信頼を磨くために~
前回は「研磨加工の歴史」についてご紹介しましたが、今回はもっと実践的な内容――**“研磨加工の現場で守るべき鉄則”**についてお話しします。
研磨は、表面をただツルツルにすればよいわけではありません。仕上がりの品質、安全性、そしてお客様の要求を確実に満たすために、守るべきルールと考え方があります。
研磨は“どの材料を、どんな目的で、どの程度磨くか”によって、やり方がまったく違います。
アルミは柔らかくて熱を持ちやすい → 低圧・高回転で
ステンレスは目が詰まりやすい → ペーパー交換の頻度を高く
セラミックは割れやすい → 常に振動と共振を避けて加工
どれだけ熟練していても、**素材の性質を無視した加工は“失敗の元”**です。
「もっと磨けばもっとキレイに」
そう思ってしまいがちですが、必要以上の研磨はかえって製品の寸法精度や表面状態を壊してしまうことがあります。
研磨は「削る」ことでもあるため、
✔ 設計公差のギリギリを攻めること
✔ 指定された表面粗さ(Ra値)を守ること
✔ 見た目よりも「機能性重視」の判断をすること
が非常に重要です。
研磨機や砥石、バフ、コンパウンドなどの道具の状態がそのまま仕上がりに影響します。
たとえば、
砥石が摩耗している → 切削力が弱くなり、加工ムラが出る
バフが汚れている → 異物混入や表面傷の原因に
ペーパーの番手を誤る → 指定Raが出ない
毎日の点検・清掃・交換を習慣化することが、製品の安定品質と顧客満足に直結します。
研磨後の製品は、「見た目はピカピカだけど、中が歪んでいる」などの**“隠れ不良”**が発生することもあります。
そこで私たちは、
平面度・寸法・厚みを定規・マイクロメーター・ゲージなどで細かくチェック
特に重要部位は測定器や検査機を用いて第三者確認
お客様との仕様打ち合わせは加工前から徹底してすり合わせ
「見た目」だけではなく、「測ってわかる精度」を重視することが、“信頼を磨く”ことに繋がります。
研磨は地味な作業に見えるかもしれませんが、高速回転する工具・熱・粉塵・騒音など、リスクが多い作業でもあります。
作業中は必ず保護メガネ・防塵マスク・手袋を着用
機械のブレ、振動、異音はすぐ停止・点検
切削くずや研磨剤はその都度しっかり除去
品質を守るには、まず安全が守られていることが前提です。事故ゼロの現場が、信頼される工場の証でもあります。
研磨加工とは、ただ「磨く」だけではありません。
それは素材を理解し、目的に応じて、精度と品質をコントロールする技術。
そして、お客様の信頼を“かたち”にする仕事です。
私たちはこの「磨く」という行為に、技術と情熱と責任を込めて、日々ものづくりと向き合っています。
次回もお楽しみに!
株式会社谷研では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社谷研、更新担当の富山です。
~石器時代から半導体時代まで、進化し続ける“磨く”技術~
今回のブログでは、私たちが日々行っている「研磨加工」という技術が、**いつ・どこで・どのように始まったのか?**という歴史的な観点からご紹介してみたいと思います。
研磨――つまり「物を磨いて滑らかにする」という行為は、実は人類の暮らしとともに数千年の歴史を持つ技術です。
研磨のルーツは、人類が石器を磨き始めた頃までさかのぼります。
旧石器時代の道具は割ったままのゴツゴツした形状でしたが、やがて石をこすり合わせて刃を整えたり、表面を滑らかにしたりする技術が生まれました。これが、**人類初の“研磨”**と言われています。
古代エジプトやローマ時代には、石や金属を装飾目的で研磨する文化が登場。
金属器や宝石、ガラス器などに磨きをかけ、美しさや光沢を引き出すために人の手と砂、植物油などを使った原始的な研磨法が用いられていました。
17世紀~18世紀の産業革命では、旋盤やフライスなどの機械工作技術が進み、金属加工の中で「研削」「研磨」が重要な工程として取り入れられ始めました。
特に機械部品の精度が求められるようになると、研磨は“見た目”ではなく“精度”を出すための技術へと進化します。
この頃から、砥石やエメリー布、ラッピング剤といった人工の研磨材も登場し、より繊細で安定した加工が可能になりました。
20世紀後半からは、半導体や光学レンズ、医療器具などミクロン~ナノレベルの高精度加工が必要な分野が拡大。
これにより、研磨加工も大きく進化します。
鏡面研磨、超仕上げ研磨、CMP(化学的機械研磨)などの高度な加工法
精密研磨機や自動制御装置の導入
表面粗さをナノ単位で制御する技術
今では、スマートフォンのカメラレンズから航空機エンジン部品、半導体ウェハーまで、研磨技術は現代産業を根幹で支える存在となっています。
“磨く”という行為は、人の暮らしの中で常に進化し、**「より良いものを、より美しく、より精密に」**という思いを形にしてきました。
次回は、そんな研磨加工の世界で職人たちが守り続けてきた「鉄則」について、実践的な視点でご紹介していきます!
次回もお楽しみに!
株式会社谷研では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()